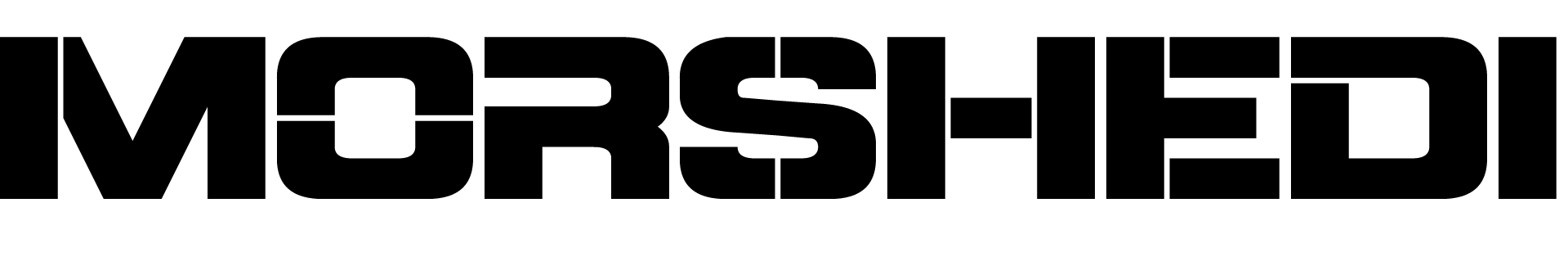なぜDXは“導入して終わり”に陥るのか
DXという言葉が経営の共通言語となって久しい。あらゆる業界でデジタル技術を活用したビジネスモデルの変革が叫ばれ、多くの企業が多額の予算を投じて新たなシステムの導入やデータ基盤の整備を進めている。しかし、その輝かしいビジョンの裏側で、現場からは「新しいシステムは導入されたが、結局Excelでの手作業に戻ってしまった」「操作が複雑で、かえって業務効率が落ちた」といった声が絶えない。
IT投資額は右肩上がりに拡大しているにもかかわらず、生産性の向上や顧客体験の革新といった本来の目的への波及効果が鈍いのはなぜだろうか。
その最大の原因は、業務を遂行する業務部門と、それを支えるシステムを構築するIT部門との間に横たわる、深刻なコミュニケーションの断絶にある。これは単なる仲の良し悪しの問題ではない。両者が拠って立つ論理体系と使用する言語が、根本的に異なることに起因する「異文化問題」なのだ。
現場が抱える「もっと顧客対応を迅速にしたい」「案件の進捗状況をリアルタイムで把握したい」といった定性的で物語的な要望は、そのままではシステム設計図に落とし込める「要件」にはならない。一方で、IT部門が語る「既存のデータベースとの整合性」「セキュリティポリシー上の制約」「処理速度を最適化するためのアーキテクチャ」といった技術的論理は、業務部門の担当者にとっては異国の言葉のように聞こえ、自分たちの業務改善の意思決定にどう結びつくのか理解が難しい。
互いが相手の言語や文化を理解しようとせず、それぞれの論理を主張し続ける。その結果、両者は互いを理解できない異文化コミュニティとして並走するだけで、決して交わることはない。そして、その断層の上にかろうじて建てられたシステムは、現場の実態から乖離し、誰にも使われないまま「高価な塩漬け資産」と化してしまうのだ。
この問題を解決するために求められるのは、両部門の間に立って会議を調整するだけの単なる「調整役」ではない。業務とIT、二つの異なる論理体系を相互に変換し、意味を正確に伝え合う高度な「翻訳機能」を担う“橋渡し人材”の存在なのである。
DXを阻む“橋渡しの勘違い”
「橋渡し人材」と聞くと、多くの人が部門間の会議を設定し、議事録を取り、双方の意見を伝達するような、コミュニケーションの潤滑油としての役割を想像するかもしれない。もちろん、そうした円滑な意思疎通の仲介も重要だ。しかし、DXを成功に導くために真に求められる橋渡しは、その次元をはるかに超えている。
ここに、典型的な失敗例がある。営業部門から「最近、案件の温度感がチーム内ですぐに共有されず、対応が後手に回ることが多い。何とかしたい」という要望が上がってきたとしよう。
単なる「調整役」としての橋渡し人材は、この要望をそのままIT部門に「営業部が、情報共有をもっとスムーズにしたいそうです」と伝えるだけで終わってしまう。これでは、IT部門は何をどうシステムに落とし込めばよいのか分からない。「情報共有ツールを導入しましょうか?」「チャットツールを活性化させますか?」といった、的を射ない提案しか出てこないだろう。
一方で、真の「翻訳者」としての橋渡し人材は、ここから深く踏み込む。まず、営業担当者にヒアリングを重ね、「案件の温度感」という曖昧な言葉を具体的な要素に分解していく。「温度感とは、具体的にどのような情報で構成されていますか?」「それは、取引先のキーマンとの接触頻度ですか? それとも、提案内容への反応の良さですか? あるいは、競合の動きでしょうか?」と問いを重ねるのだ。
その結果、「案件の温度感」が、「取引先ID」「案件ID」「商談フェーズ」「受注確度(%)」「最終接触日」「次のアクション予定日」といった、システムが扱えるデータ構造に変換される。さらに、そのデータを「担当者を横断してリアルタイムで通知するキュー」として実装し、「情報の更新が24時間滞った場合にはアラートを出すSLA(サービス品質保証)」を設ける、といった具体的なシステム設計上の論理へと翻訳していく。
逆もまた然りだ。IT部門が「この機能を実現するには、既存の顧客マスターとの連携が必要ですが、現在のデータモデルでは不整合が生じるリスクがあります」あるいは「セキュリティ方針上、外部のクラウドサービスとのAPI連携には承認プロセスが必要です」といった技術的な制約を持ち出してきた場合、それをそのまま業務部門に伝えても「よく分からないから、とにかく何とかしてくれ」という反応しか返ってこないだろう。
ここでも翻訳者は、技術的条件を業務上の意思決定の言葉に置き換える。「選択肢A:既存の顧客データを修正する。この場合、3ヶ月の移行期間が必要で、その間一部の業務が停止しますが、将来的にはより正確なデータ分析が可能になります。」「選択肢B:新たな連携は諦め、手動でのデータ入力で代替する。この場合、開発は早く進みますが、毎月10時間程度の手作業が発生し続けます。」というように、メリット・デメリットを明確にした選択肢として提示する。
このように、単なるメッセンジャーではなく、双方の論理を深く理解し、それを相手が理解・判断できる形に変換する「論理の変換者=翻訳者」としての役割を担わなければ、現場のニーズとシステムの実装が真に噛み合うことはないのである。
なぜ翻訳は難しいのか?―“二つの言語体系”の壁
この翻訳プロセスがこれほどまでに難しいのは、単なるコミュニケーション不足や知識の欠如が問題なのではない。業務部門とIT部門では、物事を捉え、思考し、表現するための「言語体系」そのものが根本的に異なっているからだ。
業務の言語は、プロセスや時間軸に沿った物語的な記述で語られることが多い。「まずお客様から問い合わせがあり、担当者がヒアリングを行い、状況に応じてAパターンかBパターンの提案書を作成する。ただし、緊急の場合はCという例外処理を行う」といった具合だ。ここには、人の判断、経験則、そして無数の「もし~ならば」という例外処理が含まれている。顧客や取引に関する記述も、背景や文脈を含んだストーリーとして語られる。この言語体系は、日々の変化に柔軟に対応し、マニュアル化できない暗黙知を巧みに扱うことに長けている。
一方で、ITの言語は、データ構造や制約条件の最適化によって世界を記述する。システムは、曖昧な「温度感」ではなく、明確に定義された「変数」や「パラメータ」でしか物事を認識できない。業務プロセスは、厳密なルールに基づいた「アルゴリズム」として再定義されなければならない。セキュリティポリシーやデータベースの正規化といった、堅牢で一貫性のあるシステムを維持するための「制約」が絶対的な前提となる。
両者は、発想の起点も、思考の前提も全く異なる体系で動いているのだ。業務部門が誇る「柔軟性」や「臨機応応変な例外対応の巧みさ」は、IT部門の視点から見れば、システムの安定性を脅かす「データの不整合」の原因や、予測不能な「仕様変更リスク」にしか映らない。逆に、IT部門が重視する「標準化」や「データの一貫性」は、業務部門からすれば「現場の実態を無視した融通の利かないルール」と見なされがちだ。
この二つの言語体系の間には、意識的な「翻訳」というプロセスを介さなければ、決して埋めることのできない深い溝がある。だからこそ、現場担当者の頭の中にある暗黙知を具体的な変数に落とし込み、複雑な業務要件を「ドメインモデル(事業領域の知識を体系化したモデル)」へと再構成し、技術的制約と業務ニーズの最適なバランスポイントを探りながら合意形成を導く、高度な翻訳機能が不可欠になるのである。
先行企業に学ぶ「翻訳機能」の制度化
この翻訳機能を個人の特殊スキルに依存させるのではなく、組織の仕組みとして定着させることに成功した企業は、国内外に存在する。彼らのアプローチは、DXの成功を目指す多くの企業にとって重要な示唆を与えてくれる。
住友商事は、2018年に「DXセンター」を設置し、2023年にはDX推進機能とIT戦略機能を統合した。これは、単に組織を一つにしたというだけではない。グループ各社の事業現場に入り込み、共に課題を発見し、解決策を実装するプロセスを横断的に推進する体制を築いたのだ。これは、各事業部門とIT部門の間に専門の「翻訳チーム」を組織的に配置し、その機能を全社的に担保した設計と言える。
エン・ジャパンのアプローチは、現場に翻訳機能を根付かせるという点でユニークだ。同社は、プログラミング知識がなくても業務アプリケーションを開発できるノーコード・ローコードツールを積極的に活用。営業や事務といった非IT部門の社員をリスキリングし、自らの手で業務を改善するアプリを構築できる人材へと育成している。彼らは、現場の課題を最も深く理解し、かつシステムの基本的な論理も分かる「中間人材」として成長し、専門のIT部門(情シス)と対等に対話できる翻訳者となる。翻訳機能を一部のエリートだけでなく、現場の隅々にまで裾野展開する優れたアプローチだ。
NECは、2019年に「Digital Enterprise Workplace」を立ち上げた際、経営陣が「出島(一部の専門部署だけがDXを進めること)は不要。全社を変革できる体制が必要だ」と明言した。その言葉通り、各事業部門に専門家が入り込み、二人三脚で伴走する仕組みを構築した。これは、翻訳者が単なる外部のコンサルタントではなく、事業の当事者として深く関与し、継続的に翻訳機能を組織に埋め込んでいくという強い意志の表れであり、全社的な変革を促す好例となっている。
海外に目を向けると、スペインのエネルギー大手Repsolの取り組みが際立っている。同社は、全社のデータを統合・活用する基盤「ARiA」を“デジタルの頭脳”として展開すると同時に、「Information College」という社内教育機関を設立し、現場人材のデータリテラシーを徹底的に育成した。これにより、内製化したデータサイエンティストと、データ言語を理解した現場担当者が直接結びつき、高度なレベルでの翻訳が可能になった。人材・データ基盤・案件創出の三位一体で翻訳機能を制度化した結果、2022年までにその経済効果は2億ユーロ(約300億円)に達したと公表しており、投資対効果の面でも明確な成果を示している。
さらに同社は、この翻訳体制を前提として、より高度な事業へと踏み込んでいる。2025年1月には、都市ごみを原料に再生メタノールを製造する「Ecoplantaプロジェクト」に8億ユーロ超の投資を正式発表した。この先進的なプロジェクトにおいても、複雑な廃棄物処理プロセスと次世代燃料の製造プラントの運転を最適化するために、データ基盤と現場運用を橋渡しする仕組みが組み込まれている。単なるデジタル投資に留まらず、翻訳機能を伴う組織体制を武器に、持続可能な未来への事業展開を加速させている点は、大いに注目に値する。
日本国内では、富士通がDXの成熟度を測る「DX推進指標」の自己診断スコアを、4年間で1.9から3.56へと大きく改善させた。ここで重要なのは、スコアの数字そのものよりも、この指標を現場と経営の言語を統一する共通の物差しとして活用した点にある。指標を通じて自社の現在地を客観的に把握し、目指すべき姿を共有することで、部門を超えた対話が生まれ、組織全体の翻訳能力が向上したと言えるだろう。
橋渡し人材に本当に求められるスキルセット
これまでの議論で明らかなように、DXにおける橋渡し人材に求められるのは、単なる人当たりの良さや調整能力といった、いわゆる「コミュニケーション能力」だけではない。それは必要条件ではあるが、十分条件ではないのだ。核となるのは、以下の三つの「翻訳スキル」である。
- 暗黙知を「変数」に変換する力現場でのヒアリングにおいて、「いい感じに」「なるべく早く」といった曖昧な言葉の裏に隠された本質的な要求を掘り起こし、それをシステムが扱える明確な「変数」や「パラメータ」に変換する能力。これは、優れたコンサルタントやアナリストが持つ、構造化思考と論理的思考力に直結する。
- 要件を「ドメインモデル」へ落とし込む力顧客、商品、契約、プロセスといった、その事業領域(ドメイン)における重要な概念と、それらの関係性を正確にモデル化する能力。断片的に出てくる現場の要望を、事業全体の構造の中に正しく位置づけ、システム全体の設計思想に矛盾なく組み込む力が求められる。
- 制約を「意思決定のフレーム」に変換する力技術的な制約、予算、納期といった避けられない制約条件を、単なる「できない理由」としてではなく、「どの選択肢を取るべきか」という業務部門が判断できるための意思決定のフレームワークに変換して提示する能力。トレードオフを明確にし、合意形成を導くファシリテーション能力とも言える。
これらのスキルは、一朝一夕に身につくものではない。しかし、エン・ジャパンの事例が示すように、ノーコード・ローコードツールは、この翻訳スキルを鍛えるための絶好の練習台となり得る。現場担当者が自らツールに触れ、業務プロセスをアプリケーションのロジックに落とし込む作業を経験することで、システムの構造やデータモデルへの理解が深まる。これにより、IT部門との対話の質が向上し、翻訳の往復速度は飛躍的に高まるだろう。
属人化を防ぐ「組織としての翻訳機能」
優れた翻訳スキルを持つスーパーマンのような人材が一人いたとしても、その個人に依存する体制は極めて脆弱だ。その人が異動したり退職したりした途端、組織の翻訳機能は失われ、再び部門間の断絶が始まってしまう。重要なのは、翻訳機能を個人のスキルセットから、組織の仕組み(制度)へと昇華させることである。
住友商事の横断組織「DXセンター」、NECの事業部門とのペア体制、そしてRepsolの基盤・人材・案件の三位一体運用は、いずれも翻訳を仕組み化した優れた実例だ。これらの事例から、組織的な翻訳機能を構築するための具体的な方策が見えてくる。
それは、「翻訳ガバナンス」とでも言うべきルールの設定だ。例えば、以下のような仕組みを導入することで、翻訳の質と再現性を高めることができる。
- 要件定義テンプレートの標準化: 業務部門が要望を出す際に、必ず記述すべき項目(目的、現状の課題、期待効果、関連データなど)を定めたテンプレートを用意する。これにより、初期段階での情報の曖昧さを減らす。
- UIプロトタイプの合意ゲート: 本格的な開発に入る前に、必ずUI(ユーザーインターフェース)の試作品(プロトタイプ)を作成し、業務部門の承認を得ることを必須のプロセス(合意ゲート)とする。これにより、完成後の「イメージと違う」という手戻りを防ぐ。
- プロジェクト初期の合同レビュー: プロジェクトのキックオフ段階で、業務部門とIT部門の主要メンバーが必ず参加する合同レビュー会を実施し、目的とゴール、そして互いの役割と制約について共通認識を形成する。
こうした仕組みを組織のルールとして組み込むことで、翻訳プロセスが標準化され、個人の能力への依存から脱却することができるのだ。
成果を測り、改善を回すためのKPI
翻訳機能を制度として組織に組み込むのであれば、その成果を客観的に測るための指標(KPI)が不可欠となる。感覚的な「連携が深まった」という評価だけでは、継続的な改善にはつながらない。以下のような定量的な観点から、翻訳機能の有効性を測定することが可能だ。
- 手戻りの削減: プロジェクトにおける要件変更の発生回数や規模が減少したか。
- システム利用の定着: リリースされた新機能のうち、主要機能が継続的に利用されている割合(利用定着率)や、一人当たりの利用頻度が向上したか。
- 価値実現のリードタイム短縮: アイデアが出てから、それが機能としてリリースされ、実際にビジネス上の価値(売上向上、コスト削減など)を生み出すまでのリードタイムが短縮されたか。
- 合意形成の効率化: 要件定義やプロトタイプの合意に至るまでの会議時間や修正の反復回数が効率化されたか。
- 資産の再利用率: 一度作成した標準部品やドメイン資産(データモデルなど)が、他のプロジェクトでどれだけ再利用されたか。
さらに、富士通の事例のように、「DX推進指標」のような外部のフレームワークを活用し、自社の立ち位置を定期的に評価することも有効だ。これにより、現場の改善活動と経営層の視点とをつなぐ共通言語が生まれ、より大局的な視点での定量的な翻訳の評価と改善サイクルを回すことが可能になる。
橋渡し人材の育成と量産の戦略
では、こうした重要な役割を担う橋渡し人材を、どのようにして育成し、組織内に増やしていけばよいのだろうか。外部から高額な報酬で“スーパーマン”のような人材を採用してくることだけが答えではない。むしろ、持続可能な組織能力を構築するためには、内部での育成と量産こそが重要となる。
そのための最も有効なアプローチは、実践を通じた育成(OJT)である。まずは比較的小規模な案件で、業務知識の豊富な現場エースと、技術に明るいIT部門の若手を意図的にペアにしてチームを組ませる。そして、ノーコードツールなどを活用して、まずは自分たちの手で要件を可視化する経験を積ませるのだ。このプロセスを通じて、現場担当者はシステムの論理を学び、IT担当者は業務の文脈を学ぶ。
住友商事が横断組織をハブとして各事業部に知見を展開するように、NECが事業部との二人三脚を徹底するように、そしてRepsolがデータ基盤と人材育成をセットで回すように、翻訳機能を特定の個人に属人化させることなく、組織全体で量産していく仕組みを構築すること。それこそが、変化の激しい時代を勝ち抜くための、企業の競争力そのものにつながるのである。
結論:翻訳こそが、DXを成功に導く核心である
DXの成否を最終的に分けるのは、導入するテクノロジーの目新しさや、投じる予算の多寡ではない。それは、現場の切実な課題を、価値あるシステム要件へと翻訳し、その要件を、ビジネスの成果という価値へと再び翻訳できるかどうかにかかっている。
橋渡し人材の役割は、単なる会議の調整役や部門間の仲介役ではない。業務とITという、成り立ちも論理も異なる二つの世界を行き来し、意味を損なうことなく正確に価値を変換する、高度な「翻訳機能」にこそ、その核心がある。
日本企業の先行例も、海外の成功事例も、その本質は、この翻訳機能を個人の資質に頼るのではなく、組織のDNAとして埋め込むための制度設計にある。
- 役割の明確化: 橋渡しを「翻訳」と再定義し、その重要性を組織全体で共有する。
- 制度設計: 人と組織を横断的につなぎ、翻訳プロセスを標準化する仕組みを構築する。
- 成果の可視化: 翻訳の成果を測る指標を導入し、継続的な改善サイクルを回す。
この三つを備え、翻訳を仕組みとして組織に定着させることができたとき、DXは「導入して終わり」の失敗から確実に遠ざかり、企業を真の変革へと導く強力なエンジンとなるだろう。